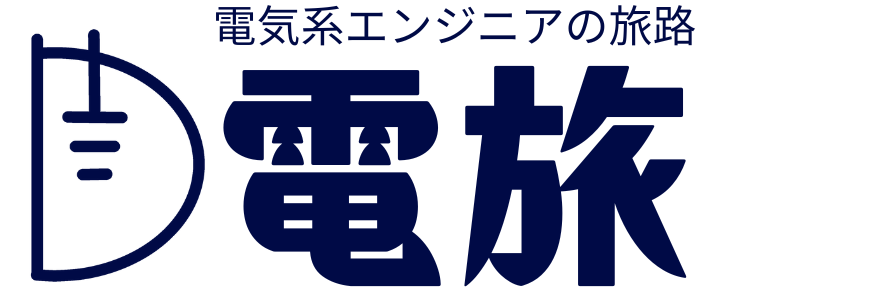この記事の目次
接地抵抗の種類
まず、前提条件として、接地抵抗は低いほど良いということがあります。
理由は、次の図で表すように、万が一漏電した機器に人が触った場合を考えると、接地抵抗が低いほどオームの法則より、より多くの電流が地面に流れて、人に流れる分が少なくなるからです。
つまり、接地が低いほど、漏電電流や過電流が地面に流れる分が多く機器や人を守る能力が高いということになります。

続いて、接地の種類について、説明していきます。
よくある接地の種類を説明する表は、次のようなものですが、これではイメージしづらいと思いますので、イラストを使って説明します。
| 種別 | 接地抵抗 | 対象施設 |
| A種 | 10Ω以下 | ・特高高圧用計器用変成器の二次側電路、高圧または特別高圧用機器の鉄台などに施す接地工事
・高圧または特別高圧の電路に施設される避雷器に施す接地工事 |
| B種 | 150/I 以下
(150を変圧器の高圧側または特別高圧側電路の1線地絡電流値で割った値) |
高圧または特別高圧電路と低圧電路が混色するおそれのある場合に、低圧電路の保護のため結合する変圧器の低圧側中性点または一端子に施す接地工事 |
| C種 | 10Ω以下 | 300Vを超える低圧用機器の鉄台などに施す接地工事 |
| D種 | 100Ω以下 | 高圧用計器用変成器の二次側電路、300V以下の低圧用機器の鉄台などに施す接地工事 |
図を使って表したのもが、次になります。
接地は地面に接地棒や銅板を埋め込むことでとります。
銅板を通して地球と機器などをつなげるイメージで、地球との接触が多いほど接地抵抗が低いです。
そのため、A種接地工事など接地抵抗を低くする場合は、接地棒をたくさん打ち込んだりして、基準値まで接地抵抗を下げます。

接地測定の方法
では、接地の測定方法について説明していきます。
接地の測定方法には、精密測定(3極法)と簡易測定(2極法)の2種類あります。
精密測定(3極法)
測定原理
測定原理は次のようになります。図と合わせて、確認してみてください。
手順は多いように見えますが、測定のために配線さえ正しくできたらあとは、測定ボタンひとつで自動で行ってくれる機器もあります。
- 測定点である接地極のほかに、補助接地極としてS、Hをとる
- EからHに定電流発生器でIを流す
- Eの電位をS点を使って測定する
- オームの法則より、V/IでRxを求める

測定前の準備
精密測定では、測定点E点のほかにP点とS点の2つの補助極を用います。
この2つの補助極は、測定点Eを測定するのを助ける接地極です。
測定時の注意点として、次の点に注意しましょう。
- 測定点は、E、S、Hの順にする
- それぞれの測定点は5~10mほど離す
- E、S、Hはほぼ一直線上になるように配置する
図で表すと次のようになります。

E、S、Hの3点はなるべく直線に配置するのがいいですが、障害物などがあって直線上に配置できない場合は、次の図のようにできるだけ30度以内が望ましいです。

測定方法
配線ができたら、いよいよ測定に入っていきます。それでは、順番に測定方法を確認していきます。
①地電圧のチェック
大地から接地極に漏れ電流があった場合、図のように地電圧VEが発生します。
このVEが、あまり大きいと測定に大きな誤差が生じるため測定することができません。
機器の仕様によって許容できる電圧が決まっており、地電圧が大きすぎるとエラー表示してくれる機器もあります。

②補助接地抵抗のチェック
補助接地抵抗値は、高すぎると測定することができません。
筆者の使用している共立の接地抵抗計の場合は、補助接地抵抗値の上限は次の表のように決められています。測定レンジによって、補助接地抵抗値の上限が異なります。
| 測定レンジ | 補助接地抵抗値の上限 |
| 20Ω | 10kΩ |
| 200Ω | 50kΩ |
| 2000Ω | 100kΩ |
補助接地抵抗値が高い場合は、エラーで教えてくれる機器もあり、その場合には、別の場所で接地を取るか、水を撒くなどして接地抵抗値を低くしましょう。
③測定
①、②の条件をクリアできていたら測定です。
測定は、簡単で筆者の使っている共立の機器では、測定スイッチを押すだけで測定してくれます。
測定レンジを選択できるため、測定結果が表示範囲を超えた場合は、上のレンジに切り替えます。
簡易測定(2極法)
測定原理
簡易測定では、測定点E点のほかにもう1つ補助極を用います。
接続方法としては、精密測定時の補助極SとHを短絡した測定です。
回路図を表すと次の図のようになります。

この回路図からわかるように、補助接地極としてSとHを短絡しています。
そのため、純粋な測定したい接地抵抗値 RXのほかに、補助接地極の抵抗値 reまで測定値に入ってきてしまいます。
一般に、簡易測定は、A種やB種の接地を利用して、D種接地(100Ω以下)など抵抗値の高めな接地抵抗を測定する場合に有効です。
測定前の準備
簡易測定では、測定点Eのほかに補助接地極を1つ設けます。
簡易測定では、補助極の接地抵抗も測定値に入ってきますので、D種接地を測定する際は、A種接地やB種接地のように接地抵抗の低いものを補助接地極として用いるとよいでしょう。
補助接地極として、変圧器2次側のB種接地極を使用した場合の測定を表したのが、次のイラストです。

測定機器のSとHは短絡するような、配線になっています。
測定方法
簡易測定の測定方法は、基本的に精密測定と同様です。
次の手順で測定を行います。
- 地電圧のチェック
- 補助接地抵抗のチェック
- 測定
さいごに
今回は、接地抵抗の種類から測定方法まで網羅的に解説しました。
この記事を、読めばあなたも接地抵抗博士になれること間違いなしです。
参考資料
デジタル接地抵抗計 取扱説明書(共立電気株式会社)