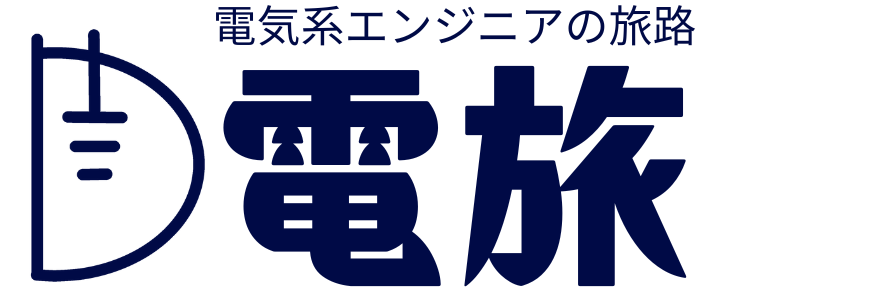電気工事では必須の知識ですので、きちんとマスターしましょう!
この記事の目次
そもそも、低圧分岐回路って何?

低圧分岐回路の施工方法
施工方法
低圧分岐回路の施工方法は、電気設備技術基準・解釈 第149条で、定められています。
低圧分岐回路の施工方法について、次の図を使って説明していきます。

- 低圧幹線から分岐した電線には過電流継電器を取り付ける。
- 基本的には、低圧幹線から分岐回路の過電流遮断器までの距離L[m]は3m以内にする。
3mを超える場合は次の条件を満たすように、施工する。
- 3m<L≤8mのとき、電線の許容電流Iwが低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流IBの35%以上にする。
- 8m<Lのとき、電線の許容電流Iwが低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流IBの55%以上にする。
ただし、注意として負荷に電動機がついている場合は、また別の考え方で許容電流値を求める必要があります。
川で考えてみよう!

施工方法の応用
先ほど、説明した分岐回路の施工方法を応用して、次の図のように徐々に電線の太さを細くしていくこともできます。
ただし、反対に電線が太くなっていく施工方法は、元の電線のほうで許容電流を超えてしまう恐れがあり、やってはいけませんので、注意してください。

低圧分岐回路の問題例
続いて、低圧分岐回路の電気工事士筆記試験の問題例を解説していきます。
低圧分岐回路の問題パターン
低圧分回路の問題では、変数がIB[A]、IW[A]、L[m]の3つありますので、主な問題のパターンは次の図で示すようになります。
主に、IB[A]、IW[A]、L[m]のうち2つが与えられていて、与えられていない1つの変数を求めるというパターンです。

応用として、求めたIw[A]から適当な太さの電線を選ぶという問題のパターンもあります。
その場合は、電線の太さと、許容電流値の書いた表があたえられますので、その表に対応させて適切な電線の太さを選びましょう。
実際の施工では、電線の種類、芯数、電線太さで許容電流値が変わってきますので、その都度確認が必要です。
低圧分岐回路の過去問題
実際に過去問を解いてみましょう!
第2種電気工事士筆記試験 令和元年下期 問9より
(問)図のように定格電流50Aの過電流遮断器で保護された低圧屋内幹線から分岐して、7mの位置に過電流遮断器を施設するとき、a-b間の電線の許容電流の最小値[A]は。

(解)本問では、前に説明した3m<L≤8mに該当します。
このため、電線の許容電流Iwが低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流IBの35%以上にする必要があります。よって、
IW=IB×35%
=50×0.35
=17.5[A]
となり、許容電流は17.5[A]と求まります。
さいごに
今回は、低圧幹線の分岐について、解説しました。条件がいくつもあり、少し難しく感じるかもしれませんが、イラストでイメージと一緒に覚えればそれほど難しくないと思います。
実際に分岐回路を施工する際も、この記事を参考に正しい施工を行ってください。