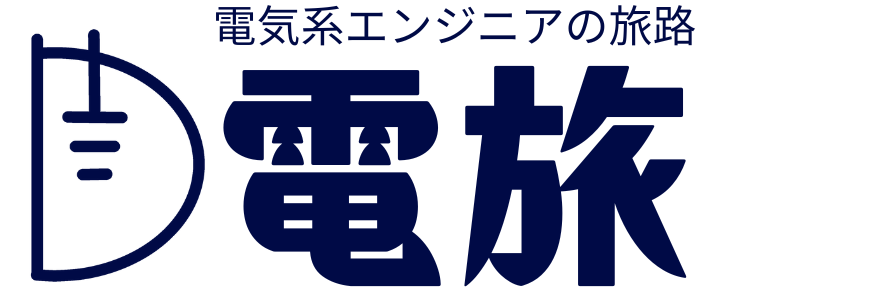- 水車の種類
- 水車の構造
- それぞれのパーツの役割
この記事の目次
水車の種類
水車は流量や高さなどによっていろいろな種類があります。水車の種類をまとめたものが次の図になります。

それぞれの水車について見ていきましょう。
衝動水車
圧力エネルギーを速度エネルギーに変えて水車に作用させます。
わかりやすく言うと、流れている水をバケットにぶつけて水車を回すということです。
水の衝撃で水車を動かすから、衝動水車と考えるとわかりやすいですね!
ペルトン水車
代表的な衝動水車で、ランナについているバケットにノズルから勢いよく水を当てて回転させます。
ノズルの先端にはニードルと呼ばれる富士山型の部品がついており、これにより水流が散らばらず、まとまって噴出することができます。

クロスフロー水車
衝動水車の一種でランナの回転軸に垂直に水が流れ込み、その勢いで、水車を回します。
反動水車
衝動水車のように水をバケットにぶつけた勢いで回すのではなく、反動水車は水が羽から出るときに羽を押し出す力(反動力)を利用します。
フランシス水車
もっとも多く利用されている水車です。
半径方向に水が流入し、ランナに力を加えつつ、軸方向に向きを変えて排出されます。
ガイドベーンの開き具合によって水の流量を調整します。

斜流水車
フランシス水車同様に反動水車で、水流がランナを軸に斜め方向に流入し、ランナに回転力を与えます。
プロペラ水車
理論的にはフランシス水車と同様で、圧力エネルギーでランナを回します。扇風機を下に向けたような形でランナがついています。
水車の有効落差
有効落差が一番高いのはペルトン水車で、800mまでの落差に対応でき、次いでフランシス水車で500mまで可能です。
斜流水車は180m程度までで、急激に低くなります。
一番有効落差が低いのはプロペラ水車で、80mまでとなります。
有効落差をまとめたものが次の表です。電験の試験にもたまに有効落差について出るので覚えておくといいでしょう。

水車を劣化させる要因
水車は様々な要因で劣化します。主な劣化原因として、水撃作用とキャビテーションがありますので、それぞれ詳しく説明していきます。
水撃作用
水撃作用は管路に水が満たされていて、負荷の急な増減により、水流が急激に変化した場合に起こります。
例えば、水撃作用が起こる場面としては、次のような場面があります。
- ニードル弁やガイドベーンを急速に動かすことにより、水流が急激に減少する(あるいは増加する)
- 落雷などにより、系統負荷が単独遮断し、系統から切り離された水車を急停止するため水口を急激に閉める場合
水撃作用の対策
水撃作用を緩和させる装置としていくつかありますので、どんなものがあるか説明していきます。
サージタンク
水撃作用を緩和させる装置としてあげられるのがサージタンクです。
サージタンクは図のように圧力トンネルの途中または、末端に設けられ、負荷の変動によって発生する水撃圧を軽減・吸収する役割があります。
サージタンクにより水量を、調整し負荷の変動に即応することができるのです。

デフレクタ
デフレクタはペルトン水車に用いられ、水車負荷が急激に変化した際に、デフレクタが動作しニードル弁から噴射している水を折り曲げて、バケットに直接当たらないようにします。
これにより、ランナの回転数を落とし、ニードル弁は徐々に閉めていくことで、水圧の急激な上昇を防ぎ、水撃作用を防止します。
デフレクタの概略を示したのが次の図です。

制圧弁
制圧弁はその名の通り、圧力を調整するための弁で、フランシス水車などの渦巻きケーシングの一部から分岐して設置されています。
ある決まった速さ以上で水口が閉鎖されると連動して開き、水圧上昇を防いでくれます。
キャビテーション
キャビテーションは次の図のように水に触れる機会部分の表面および表面近くにおいて、空気に満たされた気泡が発生する現象です。

発生原因
キャビテーションの発生原因を説明します。
圧力が下がるほど、水が蒸発する温度も低下してくるという現象があり、この水が蒸発する圧力が飽和蒸気圧です。
水車の羽などの後方では、圧力が下がってきますので、この圧力が飽和蒸気圧以下になると、水が蒸発し、気泡が発生します。この時発生する気泡のことをキャビテーションといいます。
キャビテーションによる障害
キャビテーションによって発生する障害としては次のようなものがあります。
- 水車の効率、出力の低下
- 水車が振動を起こしたり騒音を発生する
- 流水に接するランナやバケットなどの金属部分に壊食を生じ、キャビテーションが進行する
- 吸出し管入り口での水圧変動が大きくなる
キャビテーションによる障害の一つである壊食は、キャビテーションが消滅するときに局所的に高い衝撃圧力が加わり、それを繰り返すことで金属面が疲労し、水車が侵食される現象です。
キャビテーションの防止対策
キャビテーションの防止対策としては、次のようなものがあります。
- 比速度を高くとり過ぎない
- ランナやガイドベーンの表面を滑らかにする
- 吸出し管の高さをあまり高くせず、吸出し管の上部に適当量の空気を入れる
- 壊食に強い材料(13Crステンレス鋼、18-8Ni-Crステンレス鋼など)を使用する
- 過度の部分負荷、過負荷運転をしない
さいごに
水力発電は電験の電力分野で頻繁に出題されています。
今回の記事を読めば水力発電について、大体は網羅できますので、ぜひよく読んで理解してください。